|
���������玟�ɋC�ɂȂ鎖�A����͂������o�b�̔\�͂ł���B
�@�����܂Ŏg���Ă����o�b�Ƃ̍��́H �@���N���b�N�A�b�v�̌��ʂ́H �@���d�C���X���ɂȂ�ԓ����i�̃p�\�R���Ƃ̍��́H �����ɂ��Ē��ׂ邽�߁A�J�ŗ��s���Ă���x���`�}�[�N�e�X�g���s�����B 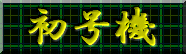 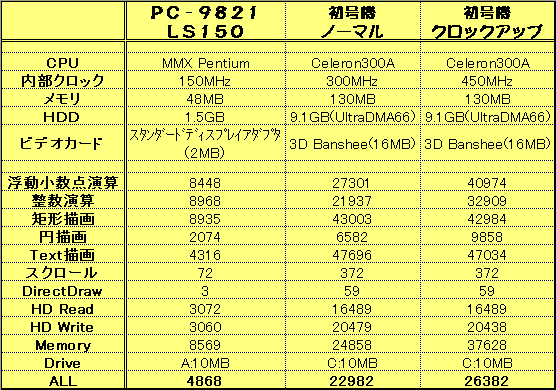
�@�k�r�P�T�O�Ƃ͎��̃��C���}�V���ł���B���������ő�S�W�l�a�܂ł������݂ł��Ȃ��Ƃ������ɂ����m�[�g�p�\�R���Ȃ̂��B�ŁA���̂o�b�Ǝ���@�Ƃ̔�r�ɂ͂�͂�傫�ȍ����o�Ă����B
�@�N���b�N�A�b�v�O�ƌ�Ƃ̔�r�ɂ����ẮA���Z�E�������[�֘A�ɍ������ꂽ�B�����_�ɂ��傫�ȊJ��������B��͂�N���b�N�A�b�v�ɂ͑傫�Ȗ��͂�����悤���B �@�킸���W�O�O�O�~���x�̂b�o�t�������܂Ŋ撣���Ă����Ƃ͔��ɂ��肪�������̂Ȃ̂����A�����ƍ������M���C�ɂȂ��Ă��܂��B���������܂�����ȃ��o�C��Ȃ��B 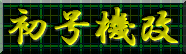 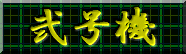 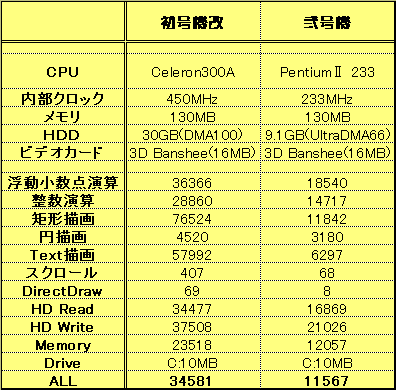
�@�z�������@�̌��ʂ��ǂ��Ȃ��B���������܂Ƃ��ȃr�f�I�J�[�h����ꂽ��ȃA�J���̂�납�B�ł��Ȃ����������Ă��K���Ȃ��B���̓Q�[�}�[�₩�瑽���̃X�y�b�N�������₯�ǁA�܂��A�Ƃ肠�����͉䖝���Ă��炤�Ƃ��悤�B�A�b�v��������Ύ����ł���႟�����B | |
|
| |
|
�@����@���^�p���Ă�����Ŏ����y���܂��Ă����ő�̃C�x���g�A���ꂪ����@�ɂ͕t�����́u�g���u���v�ł���B�V�����C�x���g���N���邽�тɏ����Ă������Ǝv���B
�y �P�U�N�S�� �z �@���w�O�̍Ō�̑g�ݗ��Ă��s�����B�����ĂP�V��ځB �@����͉��̖��p�̐VPC��g�ݏグ���B �@�v���A�悤���g�ݗ��Ă�������B�A����ɂ͂ǂ�ȕ�������납�H �y �P�U�N�Q�� �z �@�����ԁA���̂o�b���ɂ��ď������݂����Ă��Ȃ������̂ŁA�Ƃ肠������������Ă������Ǝv���B �@�䂪�Ƃ̂o�b�͂��ꂩ��������ɑ����āA�����݁u�P�U��ځv�ɓ˓������B���̂����A���ݎg�p���̂o�b�̑䐔�́u�W��v�B������������Ȃ��B�W��̓���͈ȉ��̒ʂ�B �@�P�A�䂪���C���}�V�� �@�Q�A�Q�S���ԋN���}�V�� �@�R�A���o�C���o�b�i�P�T�N�P�P���w���̂P�T��ڂo�b�j �@�S�A���̖��p�o�b �@�T�A��̖��p�o�b �@�U�A��̖��p�T�u�o�b �@�V�A�䏊�p�o�b �@�W�A���r���O�p�o�b�i�P�U��ڂo�b�j �E�E�E����ϑ������H �y �P�S�N�V�� �z �@�Еt���Ȃ��䂪�ƁA�p�\�R�����炯�B�Ƃ��Ƃ��W��ڂ��������Ă��܂����B �@����̂o�b�́A�y���e�B�A���V�W�O�O�EAX3S-PRO�E������128�E�b�c�q�v�R�Q�{�B ���܂��Ƀv�����^PM-600C�܂ł��āA��p��4.5���~�B�����������������B �@���̂o�b�A�����͐l�̎�ɓn��\��Ȃ̂����A�ꐶ���������W�߂����i�ō�����ׁA ���炭�������N���Ă��܂����B���炭�̊ԁA���낢��G���Ċy�������B �@Rasta����A�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B �y �P�R�N�U�� �z �@�Ƃ��Ƃ��c�u�c�h���C�u���Ă��܂����B �@����܂�r�f�I�������ւ\�t�g�������C���Ȃ����ŁA�ʂɔ����K�v�͂Ȃ�������₯�ǁA���i���U�X�X�X�~�ƈ����������A���܂����t���Ă������Ŏv�킸�����Ă��܂����B �@�ŁA���Ă݂���E�E�E����Ⴂ���ˁB�z���}�Y����B�����ƃ����^���s���Ă݂悤���Ǝv���Ă����B�y �P�R�N�U�� �z �@�Ƃ��Ƃ��c�u�c�h���C�u���Ă��܂����B �@����܂�r�f�I�������ւ\�t�g�������C���Ȃ����ŁA�ʂɔ����K�v�͂Ȃ�������₯�ǁA���i���U�X�X�X�~�ƈ����������A���܂����t���Ă������Ŏv�킸�����Ă��܂����B �@�ŁA���Ă݂���E�E�E����Ⴂ���ˁB�z���}�Y����B�����ƃ����^���s���Ă݂悤���Ǝv���Ă����B �y �P�R�N�S�� �z �@�Q�����瓱�������b�`�s�u�l�b�g�̑����Ɋ������A�펞�ڑ��̉��K���Ɋ������̓��X�������Ă����̂����A�o�b�P������[�^�Ƃ��ĂQ�S���ԗ����グ���ςȂ��ɂ��Ă���̂́A�d�C�ォ��݂āA���������Ȃ��Ɗ����n�߂��B�ŁA���낢��ƃR�X�g�ɂ��čl�������ʁA�䂪�Ђ����傤�ǐV���i�Ƃ��ē����������[�^�����Ă݂鎖�ƂȂ����B �@�������҂��ƂQ�T�ԁA����Ɠ͂������i���Ȃ��ł݂��̂����E�E�E���ꂪ���܂�������B����ǂ��Ă���Ă��₯�ǂȂ��B�Ȃ�ŁH �@�r�d�̋@�\�́u�C���^�[�l�b�g�ڑ��̋��L�v���g���Ă����ׂ��낤���A����Ƃ��v���o�C�_�[�̐ݒ�̖��ł��낤���A�O���ɃA�N�Z�X�����Ă���̂Ƀl�b�g�Ɍq����Ȃ��B�v�X�̔�����������̂ɂǂ����悤���Ȃ��B �y �P�R�N�Q�� �z �@�䂪���̂o�b���lj��ƂȂ�A�Ƃ��Ƃ��䂪�Ƃ̂o�b�͑����ɑ����đS�T��ƂȂ����B�����Ȃ��Ă���ƁA�ł����ɂȂ�̂̓C���^�[�l�b�g�ڑ��ɂȂ�킯�ŁB �@����܂ł́A�e�@���ʂɃA�i���O�����ʂ��Čq���ł����킯�₯�ǁA���ꂪ���������Ȃ��͖̂����B�ŁA�l�b�g�ڑ��̋��L���s�����ɂ����B �@�A�i���O�ł̋��L�E�h�r�c�m�ł̋��L�E�b�`�s�u�ł̋��L�ȂǁA�����ɖ�������₯�ǁA����͂b�`�s�u���g���čs�����B �@�T��̂o�b�̂����A�P��̓X�y�b�N���Ⴂ���߁A����ɂk�`�m�{�[�h���Q���}���ă��[�^���B��������v�����r�d�̋@�\�Ńl�b�g�̋��L���s�����B �@��A�������K�B����Ⴆ����B �y �P�Q�N�P�Q�� �z �@�䂪������w�ɍ��i�����Ƃ������ŁA�p�\�R�����V���ɕK�v�ɂȂ����B�����Ŏv�������̂��A�����P�N�ŏW�߂����i���g���ĐV���ȋ@�̂����グ�鎖�B�܂����łɎ����̋@�̂̃o�[�W�����A�b�v���}�����납�Ǝv���ĂˁB �@�ŁA�l�̎d���̓��Ӑ�ɐF�X�Ə����Ă��炢�V���ɍ���Ă݂��B�䂪�������̎q��Ƃ������ŁA�������P�[�X�̊O�ςɂ͋C���g���������B �@�����@�����ύX 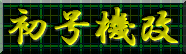 �@���p�V���ȋ@�� 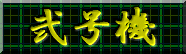 �y �P�P�N�W�� �z �@���i��g�ݍ��킹�Ăo�b�炵���������ɂȂ����܂ł͗ǂ������̂����A�n�r�̃C���X�g�[���i�K�ɂȂ��ăn�[�h�f�B�X�N���t�H�[�}�b�g�ł��Ȃ��������������B�a�h�n�r�i�K�ł͔F�����Ă���̂ɂȂ��H �@���_��UltraDMA66�Ή��̃h���C�u�ł������̂ɁACD-ROM�h���C�u�Ƃg�c�c�Ƃ��v���C�}���̂h�c�d�X���b�g�ɗ����Ƃ��q���ł������ɂ������l���B����̓E�F�X�^���f�W�^���̃h���C�u�łȂ�������N����Ȃ������炵���B �@���ǁAUltraDMA66�R���g���[�����w������CD-ROM�h���C�u�ƕʁX�ɐڑ����鎖�Ŗ��͉��������B���x�͂h�a�l�̃h���C�u���l�ɂ��悤�B �y �P�P�N�W�� �z �@WindowsNT�̃C���X�g�[�����I���A�N�����m�F���āA���Ă��ꂩ��g���{�[�h��t���Ă������ƍ�Ƃ��n�߂���A�k�`�m�{�[�h���������_�ŃC�x���g�r���[�A�ɐԃ}�[�N���₽��o�Ă���l�ɂȂ��Ă��܂����B �@�C�x���g�r���[�A������@����ɁA�ǂ����h���C�o�ɖ�肪����炵���B�������ʂ�ɃC���X�g�[�������̂ɉ��́H �@���͂k�`�m�{�[�h�̐������ɂ������B�m�s�p�̃h���C�o�͂e�c�̃T�u�f�B���N�g����ɂ���̂ɁA��������ł̓��[�g�f�B���N�g���ɂ���Ə�����Ă����̂��B�e�c�̒��g���J���Ă݂���u\NT\�v�����������߁A���̒��̃h���C�o�������ɃC���X�g�[�����Ă݂��Ƃ��낤�܂��������̂ʼn��������鎖���ł����B �y �P�P�N�W�� �z �@�^�p���n�߂Ă��炭���������ABIOS��ɂ���n�[�h�E�F�A���j�^��`���Ă݂��Ƃ���A�b�o�t�̉��x���V�O���߂��ɒB���Ă��鎖�ɋC���t�����B�R�������炢��������B �@�ŁA�t�@���̉�]�����グ�邽�߂ɓd�����j�b�g���璼�ڏo�Ă���d�����t�@���ƂȂ��ł݂��B���������������ς��Ȃ������B �@����ł͂܂��}�Y�C�I���߁A�O���X�̓h�蒼�����s���Ă݂��B�������炱�ꂪ�₽�炫�����B�b�o�t���x�͂P�O���߂���������A�U�O��������鐅���ɂ܂ŗ������ɐ��������B �@���_�́A�O���X�̓h����������������ɂ������悤���B�g�ݗ��Ă�ۂɎQ�l�ɂ����{�ɂ́u�O���X�͔�����Δ����قǗǂ��v�Ə�����Ă������߁A�����^�Ɏċɔ��h������Ă��܂��Ă����B�ʂɂ��̎w�E���Ԉ���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂����A���߂����肩�͓h��߂��̕����܂��܂��ł���Ə��������Ă����ė~���������B �@����A���x��̏d�v�����g�ɂ��݂����߁A�P�[�X�w�ʂ̎��R�r�C�d�l�������r�C�d�l�ɕύX�����B �y �P�P�N�X�� �z �@�^�p���A�ˑR��ʂ��t���[�Y���Ă��܂����B���̂����̂��Ɩ����̐o�����s���Ă����̂����A���ɖ�肪���t����Ȃ��B�����A�r�f�I�J�[�h�������₽�甭�M���Ă����B�t���[�Y�̗��R�͗ǂ�������Ȃ��̂����A�ЂƂ܂��r�f�I�J�[�h�̔��M��}���Ȃ���ƍ�Ƃ��J�n�����B �@�܂����Ă݂��̂��A�r�f�I�J�[�h�̃q�[�g�V���N�Ƀt�@�������t���Ă݂鎖�B���ʃe�[�v�ŕt���Ă݂��̂����A���ꂪ�S�����܂������Ȃ��B�M�Ŕ�����Ă��܂��̂��B�Ȃ�Ίg���X���b�g�ɑ�^�̃t�@����t���ċ����r�C�����悤�ƍl���A�t�@�����Ă����̂����A�������Č��ԂɎ��܂肫��Ȃ������B �@�������̂��̖��A�ǂ�������ǂ����̂��B �y�P�P�N�P�O���P�W���z �@���̂Ƃ���A���܂莩��PC���g��Ȃ��B���ł���B �@�Ȃ��g��Ȃ��̂��A����́A���f�����t���Ă��炸�A����OS��NT������ł���B���f�����Ȃ�����[�����o���Ȃ����A�C���^�[�l�b�g�ɐڑ����邱�Ƃ��o���Ȃ��B�Ƃ������Ƃ͖��������グ��K�v���Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�܂��AOS��NT�ł���Ƃ������Ƃ́A�g���Ȃ��\�t�g�����Ȃ肠��Ƃ������Ƃł���B �@���f���́A�g�ݗ��ē����Ƀ��[���E�l�b�g�͋��}�V���ōs���ƌ��߂Ă������ߕt���Ȃ������BOS�ɂ��Ă͎����̂�����肩�瓱�������B�ǂ���珉���̂��̌��܂莖�ɋT�����Ă����悤���B �@���낻�냂�f���̕t�����Ȃ̂��낤�B �y�P�P�N�P�O���R�O���z �@����ƃ��f���������B���������܂��q����Ȃ��B �@����̎���������NT�Ɍ����Ȃ�����������g�����Ƃ��Ă��邽�߂��A�A�J�E���g�̔F�ؒi�K�Ŗ������������Ă��܂��̂ł���B���̂X�W�ł͓�������ł����܂������Ă�̂ɁE�E�E�B�t�F���C�g�R�A�̂����������̂��낤���A����Ƃ��l�b�g���[�N�̐ݒ肪�����̂��낤���H�B �@����ɉ����A�����@�X�W�ɃC���X�g�[������Windows�X�WSE�̋@�\���g���Ď���@��ʂ��ăl�b�g�Ɍq���悤�Ƃ����̂����A������܂����܂������Ȃ��B������SE���C���X�g�[�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H �@���������̓��X�������������B |
|
| 2004/0�S/�P�T |